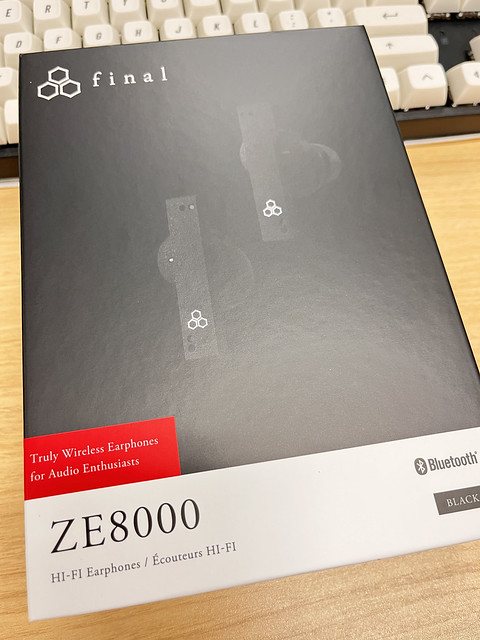2026/02/01

Apple iPhone Air
普段使い用カメラとして富士フイルムのX halfを購入しました.
いままで普段使い用カメラとしてはリコーのGR III Diary Editionを使用していましたが、それを下取りに出しての入れ替えとなります.
GRシリーズは新型のGR IVが発売されていますが、争奪戦となっており抽選販売に何度申し込んでも当選せず購入することができません.ネット上での抽選販売では転売目的などの申込みも多いであろうことから昨年末に原宿にあるリコーの直営店であるGR SPACE TOKYOに出向いて店舗の抽選販売に申し込みましたがそれもハズレとなってしまい、落選回数も7回を数えるに至りました.
メーカーに文句をいうのは筋違いかもしれませんが需要を満たすだけの生産量を確保できないという点では不満も出ようというものです.
冷静になって考えると、GRにそこまでの価値があるものか疑問にすら感じてきましたので一度河岸を変えてみようかと思い、他メーカーのラインナップを調べましたが、明確な対抗機種がないのですよね.単焦点の画質重視の高級コンパクトカメラという製品はキヤノンはフィルムカメラの時代含めて長いこと出してないですし、ニコンはCoolpix A以来音沙汰なし、ソニーは画質に振り切ったRX1R IIIで対象外.
富士はX100VIが選択肢としてありますが、すでにこれは所有しており、通勤鞄に日々忍ばせるにはちょっと大きいのですよね.
富士にはもう1つ選択肢があり、それがX halfなのですが、
・日頃から通勤鞄に忍ばせておくことのできる手頃なサイズ感
・ファインダーがついている
という点は魅力なのですが、店で触ってみると、
・窮屈で指の収まりが悪いグリップ
・プラスティッキーでチープな外観
・小さくて見づらいモニタ
・遅いAF
・機能を抑えているわりに使わなさそうなエフェクトがてんこ盛り
と難点が多く、何度も店頭でいじるも「これはないな」と見放すこと数回.
しかしGRから距離を置きたくなってくると「意外とこれ、いいのでは?」と思うようになり、一度手を出してみるかと購入に至ったというわけです.
ちなみにGR III Diary Editionは恐ろしいことに購入時と大差ない金額で下取りされ、X halfを購入しても2万円ほどお釣りが来ました.さらにX halfは15,000円のキャッシュバックキャンペーンを行っていますので、35,000円も返ってくることになります.この需要、やはりどこかおかしいです.

Apple iPhone Air
購入はいつもの中野のフジヤカメラ.そして同じビルに入っているルノワールで開封とセッティング、試し撮りを行うまでがいつもの流れ.
ピザトーストが厚切りで存在感があるためか、X halfが小さく見えます.縦横のサイズで比較するとGRより5mm程度しか小さくないのですが、現物を手にしても随分と小さく感じられます.
ボディカラーは店頭でプラスティッキーに感じられたシルバーの他にブラックとガンメタリック系のチャコールシルバーの3色.今回は質感的に無難そうに見えたブラックを購入しました.

FUJIFILM X half
いつものように1枚目は注文したコーヒーを撮影…… なのですが、X half特有の機能を最初から使ってみようと思い、2in1と呼ばれる2枚の写真を1枚にまとめる、組写真的な機能を試してみました.設定をまったくいじらずに撮影したのでホワイトバランスも寒色気味で、2in1も右→左の順番で撮影されています.組写真というもの自体、いままでやったことがないので組み合わせの妙のようなものがよよくわからないです.
撮影時に巻き上げレバーを模したパーツを巻き上げることで2in1モードに入りますが、あとから専用アプリ上で写真を選んで作成することもできます.とはいえ、その場の判断で組み合わせの妙を作り出すのが撮影の楽しさともいえるかもしれません.

FUJIFILM X100VI
X halfの正面.富士お得意のクラシックな風合いをしたデザインです.光学ファインダの横にある擦りガラス状をしたものは二重像合致用ではなく、LEDフラッシュを擦りガラス風に仕立てたものです.
レンズは35mm換算で32mm.こんな中途半端な焦点距離にした理由は「写ルンです」と画角を合わせたため.ただ、個人的に21mmレンズをAPS-Cフォーマットで使った時の画角が好きなので、焦点距離32mmは歓迎ですし、このカメラを選んだ理由の1つでもあります.

FUJIFILM X100VI
上面.手書き風のX halfの文字がいいですね.しかもFUJIFILMのロゴともどもプリントではなく刻まれています.機能的に難点はあれど、こうしたところに手を抜かないのが面白いところでもあり、このカメラのキャラクタを示しているようにも思えます.
アクセサリシューもありますがフラッシュ用接点はなし.いわゆる「コールドシュー」と呼ばれるタイプのものです.
巻き上げレバーのようなものは先述した2in1用のスイッチです.と同時に親指を引っ掛けてホールド性を高めるサムレスト的な使い方もできます.
露出補正ダイアルが用意されているのは美点です.ただしクリック感はやや眠いもので、±0にしたときに判別できるように感触を変えるような芸の細かさはありません.
レンズ部分にMF時のピントリングと絞りリングがあるのもいいですね.ただ、1インチセンサーということもあって被写界深度をあれこれいうほどのボケも望めないので基本的にはAポジションにセットしてプログラムモードで撮影しています.また、AFからピントリングを回すことでMFモードに切り替わるような便利機能は付いていません.

FUJIFILM X100VI
背面.このカメラが他とは違うと感じさせられる要素がいくつも見受けられます.
まず液晶モニタが縦長です.「X half」という名が示すように、ハーフサイズカメラ(フィルムを節約するために1コマ36x24mmを半分にして2コマ撮影できるカメラ)を模しているのでカメラを普通に構えると縦長の写真が撮影されます.センサーは1インチで画素数は約1774万画素.これを縦位置でアスペクト比3:4で配置しています.個人的には3:2のアスペクト比が好みなのですが、3:2を縦位置で撮影するとやや縦長に感じられるので縦位置がデフォルトであれば3:4もアリかなと思います.
左側にあるフィルム窓のようなものは富士フイルム機の最大の売りともいえるフィルムシミュレーションの選択用ディスプレイです.上下にスライドさせることで切り替えることができます.ちなみに撮影画像表示用モニタとフィルムシミュレーション用ディスプレイは同じ1枚の液晶モニタだそうです.
やや見づらいですが中央部の大きな四角形がAF測距枠です.中央に加えて上下左右の9箇所でAFが機能しますが手動選択のみでオートエリアAF的な機能はありません.しかもAF測距枠のサイズも変えられません.オートエリアAFはなくても構わないのですが、AF測距枠は小さくしたいところですね.
光学ファインダが内蔵されているのは個人的に高評価です.AF合焦位置どころかまったく情報表示がなく、パララックスの目安すらありませんが、ファインダを覗いて撮影するのは楽しいものなので存在するだけでも十分です.

FUJIFILM X100VI
項目は少ないですが、カスタマイズもできます.
設定画面では左側のフィルムシミュレーション表示窓にもメニュー項目や設定反映ボタンなどが表示されます.

Apple iPhone Air
X100VIと比較.価格差が2.5倍近くありますので比較するのは酷というものですが、外観の質感から始まり内部の機能に至るまで、あらゆる部分に性能差があります.

FUJIFILM X half
1/420秒 F5.0 ISO200
フィルムシミュレーション PROVIA
フィルムの粒状性を再現したというフィルムグレイン機能が搭載されているので、弱設定で粒状性小さめで撮影しましたがX100VIと比べてもかなり強めにかかります.ちょっとこれではザラつきすぎでは、ということで早々にオフにしてしまいました.

FUJIFILM X half
1/450秒 F5.6 ISO200
フィルムシミュレーション PROVIA
こちらがフィルムグレインをオフにしたもの.スマートフォンくらいのディスプレイサイズだとフィルムグレインをオンにしておいても違和感がなく程よい画質に見えるのかなという印象ですが、拡大するとやり過ぎ感がありますね.

FUJIFILM X half
1/140秒 F3.2 ISO200
フィルムシミュレーション Velvia
派手目の被写体にはフィルムシミュレーションVelviaを.
フィルムシミュレーションは現在20種類ありますが、一部を除いた13種類が搭載されています.
背面のフィルム確認窓のような液晶をスライドさせて切り替えるのですが、使わないフィルムシミュレーションを非表示にできたり並び順を変えることができたらいいのにと思いました.
また19種類ものアドバンストフィルター(トイカメラやミニチュアなどのエフェクト)も搭載されていますがこちらもフィルムシミュレーションと同様にスライドさせて選択するのが煩雑で、いまのところ使っていません.

FUJIFILM X half
1/1000秒 F7.1 ISO200
フィルムシミュレーション クラシッククローム
こちらはフィルムシミュレーション、クラシッククローム.被写体に応じてフィルムを交換するかのように色調を変えられるのが富士フイルム機のいいところです.

FUJIFILM X half
1/400秒 F5.0 ISO200 露出補正+1
フィルムシミュレーション PROVIA
カメラの性格的にトイカメラに片足突っ込んだ雰囲気もありますが、レンズは非球面レンズ3枚を含む5群6枚という高品質なもの.
しかしながら直射日光が入ると派手にゴーストが出ます.意図的にこうしたレンズ設計をしているとしたら富士フイルムさすがだなと思います.

FUJIFILM X half
1/125秒 F2.8 ISO1600 露出補正+2/3
フィルムシミュレーション Velvia
最短撮影距離はレンズ前10cm.料理写真などにも十分対応できますが、ミックス光源下では色味が青に振れることが多い気がします.ホワイトバランスはケルビン値での指定は可能ですが、テーブルナプキンなど白いもので合わせるマニュアルプリセット機能はありません.
2週間ほど使ってみた感想としては、
○ コンパクトなボディサイズ
△ レンズの出っ張りが収納できるとなおよし
○ 情報表示はないものの光学ファインダを内蔵している
× AF精度が低くてピンボケ写真になることがある
× 画面サイズが小さいので拡大しないとピンボケが判別できない
○ 画角32mmは個人的に好み
× AF測距枠が大きく、調整できない
× ホワイトバランスのマニュアル設定ができず、色調調整もできない
× 露出補正や絞りリングのクリック感がチープ
○ バッテリがX100VIと共通でサイズも大きめなのでバッテリが長持ち
と難点は多々あるものの、普段使い用カメラとしては十分だと感じました.とはいえ、万人に勧められるカメラでもないかなという印象です.
GRやX100シリーズのように「カメラを使いこなす」という目的で選ぶと肩透かしを喰らう可能性がありますね.もともとそういう想定で作られたカメラではないともいえそうですが.
フィルムカメラモード搭載や、35mm換算で32mmレンズという焦点距離が採用されているように富士としては『デジタル版写ルンです』を作りたかったのでしょう.なのでポケットに無造作に突っ込んでおいて気になったものはとりあえず撮っておく、みたいな使い方が似合いそうでもあります.
2025/12/31
1年を振り返る、物欲篇です.
昨年は大物(ロードスター)を購入したので、それに比べると控えめです.その割に懐具合が寂しいのはやはり物価高のせいでしょうか.
■カメラ・光学
4月:Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical
5月:Nikon MIKRON 6×15 CF
■コンピュータ
9月:Apple iPhone Air
■オーディオ
2月:final ZE8000
3月:final S4000
12月:final TONALITE
■家電
5月:SONY REON POCKET PRO
■その他
5月:MAZDA SPIRIT RACING ドライビングサングラス
9月:SUWADA つめ切り DIAMOND
11月:GARMIN eTrex Touch
12月:Kindle Colorsoftシグニチャーエディション
■カメラ・光学
4月:Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical

CP+で試し撮りして気に入ったレンズです.近い焦点域のレンズとしてVoigtlanderのAPO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical IIを持っていますが、こちらが絞り開放からシャープで隙のない画像であるのに対し、このレンズは絞り解放で柔らかい描写、絞るとシャープな描写となり、変化をつけることができるのが楽しいレンズです.
F値が1.2と明るいレンズなので夜の撮影にも強いのもポイントです.
5月:Nikon MIKRON 6×15 CF

もともとは社内のレイアウト変更によって遠くのホワイトボードを見る必要性があって双眼鏡を買おうと思ったのがきっかけです.
安くていいものも多々ありますが、100年以上前から続くデザインに惹かれてこちらを購入しました.コンパクトでありながら質感が高く重さもあって「いいもの」感がありますね.
基本的には社内に置いてあり、必要に応じて持ち出す感じです.
■コンピュータ
9月:Apple iPhone Air

iPhone 13miniからの買い替えです.小型のiPhoneが欲しかったのですが不人気機種らしく後継機も出る気配がないので、薄型のiPhone Airを購入しました.
世間的には小型のiPhone以上に不人気機種のようですが、個人的には気に入って使っています.
■オーディオ
2月:final ZE8000
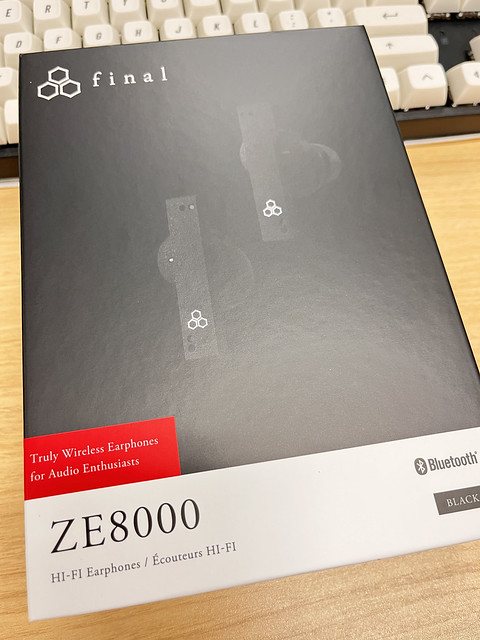
2022年にZE8000を購入し気に入って日々使っていましたが、発売から3年くらい経過したこともあって値段も当初の1/3近くまで下がったタイミングで予備機を購入しました.
後述するように、同じfinalのTONALITEを購入しましたので、こちらはどうしようかという感じです.
3月:final S4000

2024年11月にfinal S5000を購入し気に入って使用しており、同系統のシリーズとしてS4000を購入しました.
フルレンジ2BA機というスペックは同一ながら筐体の素材が異なっており、S5000の真鍮筐体に比べてS4000のステンレス筐体はすっきりとしたクリアな音質なのが特徴です.
12月:final TONALITE

2022年にZE8000を購入してから3年、ワイヤレスイヤホンを変えずに使い続けてきましたが、ここでようやく興味の出たイヤホンが登場したので購入しました.最大の特徴は頭や耳の形状を計測して、その人に合わせた音色に調整してくれる機能を搭載していることです.
調整後に聴いてみると当初は「まあたしかに良くなったかな」というくらいの印象でしたが、調整前の音色に戻すと全然違うという印象を受け、そして様々な曲を聴くと音の違いに驚かされます.
■家電
5月:SONY REON POCKET PRO

自分が使用していた旧型のREON POCKET 3と比べて大幅に機能アップ(と同時にサイズもアップ)したので購入しました.
冷温を伝えるペルチェ素子の面積が大幅に拡大されてバッテリ容量も大型化されたことで、夏場の出勤時などにも旧型では出勤時でバッテリを使い切ってしまっていたのに対して、こちらは帰宅後でもまだバッテリ容量に余裕があり、ギリギリ2日間使えるかなという感じなので使用時間的には4倍程度になっています.
■その他
5月:MAZDA SPIRIT RACING ドライビングサングラス

運転用のサングラスはいくつか購入して試したのですが遮光率が高いとトンネル内で見づらかったりと、なかなかいいものが見つけられなかったのですが、マツダ純正ともいえるこのサングラスは車両開発部門が協力しているとのことでこれなら問題ないだろうと購入しました.
トンネル内でも視界が確保されつつも逆光での使用に耐えられる絶妙さが気に入っています.
9月:SUWADA つめ切り DIAMOND

新潟旅行の際に工場併設の店舗にて購入しました.
爪切りとしての切れ味や機能的な部分は同じですが、サイズやグリップの仕上げなどでバリエーションが用意されています.購入したものはグリップ部分がダイアモンドカットされており、それが気に入って選びました.
11月:GARMIN eTrex Touch

昨年購入したeTrex Solarでログが取れないという不具合が頻発し、どうやら歩行を前提とした製品ということで長距離・長時間の使用には難があるようなので、出たばかりのeTrex Touchを購入しました.
ローエンド機であるeTrex Solarがメモリ容量28MBなのに対して、eTrex Touchは32GBと文字通り桁違いであり、eTrex Solarに比べてカスタマイズ性も高く、動作安定性や記録後のデータ転送面などでも使い勝手が改善されています.
12月:Kindle Colorsoftシグニチャーエディション

いままで使用していたKindle Oasis(2019年モデル)からの買い替えです.
E inkがカラー対応になったのが最大の特徴です.小説を読むのにカラー画面の必要性はないのですが、メールマガジンや漫画なども読むのでやはりカラーは必要だなと感じました.また端子がmicroUSBからUSB Type-Cになったのも大きいですね.
ネックだったのは価格.定価だと44,980円もします.以前は1万円を切る価格だったのを考えると、カラーになったとはいえ高くなったものです.しかしAmazon端末といえば待っていればセールで値下げされるのが常.ブラックフライデーセールで1万円引きになったところを購入しました.
来年の物欲はどうでしょうね.
手持ちのRICOH GR III Diary EditionをGR IVやGR IIIx HDFに変えたいなと思いつつも、7回も抽選に外れている有様ですのでそろそろ当選してもいい頃合いなのではと思うのですが、これだけ人気なので他のメーカーから対抗機が出てもいいような気もするのですが、残念ながらその兆候はなさそうです.
2025/10/19
半年ほど前ですが、Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Asphericalを購入しました.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/80秒 ISO100
きっかけは今年3月に行った、CP+のコシナブースでこのレンズを試したことでした.
当時、メインのレンズとして同じVoigtlanderのAPO-LANTHAR 35mm F2を使用していました.解放からキレのいいレンズでII型になって最短撮影距離が27cmまで寄れるようになるなど、焦点距離含め自分にとっては理想のレンズです.
が、このNOKTON 40mm F1.2は絞り開放時の「ユルさ」「柔らかさ」がAPO-LANTHARにはない魅力でした.それでいて絞ればキレのよさもあり、絞り値によって描写を変えられるのが気に入り、購入することにしました.
少し気になったのは焦点距離.個人的に好みの焦点距離は28mmから35mmくらいなので40mmだと望遠寄りかなと思いましたが、CP+で触った時もそれほど違和感がなかったので購入に踏み切りました.

Apple iPhone 13mini
F1.2という明るいレンズながら前玉はそれほど大きくないですね.フィルタ径は58mmでAPO-LANTHAR 35mm F2と同じです.Voigtlanderのレンズキャップはバネが弱いのと引っ掛かりがよくなくて外れやすいので予備を常備しているのですが、使い回しできるので助かります.
モダンクラシックなデザインのレンズで、Zfとの組み合わせで違和感がありません.絞りリングは先端寄りにあり、細めですが操作しやすいです.

Apple iPhone Air
フードはねじ込み式で、内側にネジが切ってあって58mmフィルタが取り付けできるようになっています.なのでフィルタをつけても全長が伸びません.ただし、つけ外しはしづらいので一時的に使うようなフィルタはレンズとフードの間につけたほうがよさそうです.
自分は日中の屋外でも絞りF1.2解放で使えるようにND8フィルタをつけています.室内や屋外でも暗くなって光量の低い環境ではフードごと外して撮影しています.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/200秒 ISO100
絞り解放、最短撮影距離で撮影.収差で霧がかかったかのようにふわっとボケています.しかしながらピントの合っている部分はしっかりと描写されています.昔の単焦点大口径レンズは絞り解放で撮影距離が短いとピントの合っているところも収差がありすぎてユルく、2段くらい絞らないと使えなかったりしたものですが、これであれば解放から使っていけます.ただし、ピントの合っている範囲が狭すぎるので必要に応じて絞った方がいいでしょうね.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F5.6 1/800秒 ISO100
屋外でF5.6まで絞って撮影.同じレンズとは思えないほどキレのいい描写です.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/1600秒 ISO100

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F2 1/800秒 ISO100
絞り解放ですと周辺減光が強めに出ます.F2まで絞るとほぼ気にならなくなります.
周辺減光も描写表現として変化がつけられて気に入っているところです.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/1250秒 ISO100
絞り解放で撮影.こうした花の撮影などでは収差がプラスに働きますね.
ピントの合っているところもふわっとしていますが、ピントの芯はしっかり出ているのがいいですね.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/1600秒 ISO100
同じく絞り開放ながら、やや離れたところにピントを合わせると収差も抑えられた描写になります.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F7.1 1/40秒 ISO1400
画角40mmなのと、最短撮影距離30cmなので新幹線などでテーブルのものを撮影するのにちょっと引きが足りないかなと感じる部分はあります.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F2 1/40秒 ISO360
F2まで絞って撮影.1段半絞ることで周辺減光も控えめになり、近接域でも安定した画質になります.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/125秒 ISO250
ふわっとした収差、ピントの合っている場所の存在感、周辺減光が相まって立体的な描写を感じます.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/2000秒 ISO250
ややノスタルジックな色味で撮影したら、ジオラマを撮影したかのような雰囲気が出ました.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/40秒 ISO2000
夜を意味するNoktから名付けられたNOKTONだけあって、夜の撮影でも絞り解放F1.2が威力を発揮します.
夜間の神社の薄暗い照明でも絞り解放、1/焦点距離のシャッター速度でもISO2000で撮影できるのは明るいレンズならではです.
同じVoigtlanderでもAPO-LANTHAR 35mm F2は絞り解放からシャープな画質で、絞りはシンプルにボケ具合を加減するものという性質なのに対し、このNOKTON 40mm F1.2は画質のユルさやシャープさ、周辺減光による空気感のようなものまで絞りで調節できる自由度を感じます.
2024/12/31
1年を振り返る、物欲篇です.
こんなに買い物したっけ?と思うほどの量になっております.
■カメラ関連
1月:Nikon Zf
1月:NIKKOR Z 26mm f/2.8
3月:NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
3月:NIKKOR Z MC 50mm f/2.8
3月:Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical
7月:FUJIFILM X100VI
12月:Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical II
■コンピュータ関連
4月:Keychron Q2Pro
6月:iPad Pro M1 12.9inch
8月:Logicool MX ERGO S
■オーディオ
12月:final S5000
12月:Astell&Kern AK HC3
12月:iFi audio xDSD Gryphon
■車
4月:MAZDA ND5RE Roadster
■家電
2月:BALMUDA ReBaker
10月:日立 洗濯機
11月:Panasonic ジェットウォッシャードルツ
■その他
1月:GARMIN eTrex Solar
3月:MONDAINE Evo2 35mm
4月:Organ M-7
7月:五藤工学研究所 GT-M518
8月:GARMIN vivosmart 5
■カメラ関連
1月:Nikon Zf

RICOH GR III
Zfを購入したのはやはりこの外観.フルフレーム機で性能は中級機クラスと、自分の使い方にもあっていたというのもあります.
と同時に、いままで10年くらい使い続けていた富士フイルムXマウントへの不満や不安(X-Pro3の液晶可動部損傷リスクやレンズが徐々に大きく高くなってきていること)もあって、結果としてマウント乗り換えということにつながりました.
基本はMFで撮影することが多いのですが、見やすいファインダも気に入っています.
1月:NIKKOR Z 26mm f/2.8

RICOH GR III
Nikon Zfをレンズキットではなくボディ単体で購入したので、とりあえず1本レンズを買っておこうと思い入手したもの.
持ち運びしやすさを重視したパンケーキレンズと言われるような製品ですが、性能に手ぬかりはなく画質も不満はありません.
3月:NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

FUJIFILM X100V
Zマウントユーザなら買っておけと言われるレンズです.
24-120mmという必要十分な画角を備えつつも、F値固定、テーブルフォトもいけて、画質は文句なし、という納得の逸品.
単焦点レンズと比べて大きく重たいので持って出ることはそれほど多くはないのですが、さまざまなシチュエーションでの撮影が考えられるような時は持って行っており、期待は裏切られません.
3月:NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

FUJIFILM X100V
上記の24-120mmと下記のAPO-LANTHAR 35mmとあわせて同時に購入しました.
3本も同時に購入できたのは、X-Pro3とXマウントレンズ一式を下取りに出したからで、このときが正式にマウント切り替えしたタイミングとなります.レンズもさることながら、X-Pro3がそこそこいいお値段で売れたので、レンズ3本買っても手元にお金がそこそこ残るくらいでした.
その売却したレンズにXマウントレンズの60mm F2.4 Macroが含まれており、その後継として買ったものです.60mm F2.4 Macroはフルフレーム換算すると90mmなので、NIKKOR Z MC 105mm F2.8 VR Sのほうが画角的に近いのですが、高価であることと中望遠の焦点域が苦手ということもあってMC 50mmを選びました.AFは速くないのですが、使用用途を考えると速射性は求められないので問題ありません.画質的にも不満がなく、小物の撮影などに重宝しています.
3月:Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical

FUJIFILM X100V
焦点距離35mm、MFという個人的趣向に偏ったレンズです.
稼働回数はZマウントレンズの中でも最も多く、Zfにつけっぱなしです.
APO-LANTHARという名称がつくように、コシナVoigtlanderブランドの中でも高画質レンズ設計のシリーズであり、なにを撮っても文句のない画質です.
弱点は最短撮影距離35cmと寄れないこと.料理の写真を撮るときなどで小鉢のようなものだと歯痒い思いをすることがあります.
購入後しばらくして販売終了となり、そして12月にII型にリニューアルされて外観デザインの変更とともに最短撮影距離が27cmに変更となりました.ので、発売のタイミングでII型に買い替えました.
7月:FUJIFILM X100VI

RICOH GR III
X100Vから買い替えにて入手しました.
X100Vが2020年2月の発売で4年経過したモデルながら、モデル末期になってさらに需要が高まって購入できない方が出ている状況での新型X100VIの発表、そしてX100VIの価格がX100Vの発売当時の価格より10万円ほど高価であること、そんな状況ながら予約殺到でまったく買えない状況が続くという、カメラとしての性能や画質以外のところで話題を集めたカメラです.
X100Vからの変更点として、高画素化や手ぶれ補正機能の搭載などそれなりに手が入ってはいるとはいえ、10万円アップという価格にはさすがに自分も躊躇して様子見をしていました.ところが、X100VIの入手困難に影響されてX100Vの買取価格が上昇を続け、4年前の購入時の価格を上回り、さらにはX100VIの新品価格に近いところまで来てしまいました.それならば…… ということで、いつものカメラ店の抽選販売に申し込んで当選し、X100Vを下取りにして入手しました.なので実際に支払った金額は12,000円くらい.買っている側としても意味がわかりません.
それはさておき、画質も機能面でも非の打ちどころのない、よくできたカメラです.レンズはX100Vと共通でフィルタやフードなどのパーツ類もすべて使い回しできるのでその点でも自分にはプラスでした.
12月:Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical II

Apple iPhone 13mini
3月に購入した、Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2 AsphericalのII型です.違いは外観と最短撮影距離が35cmから27cmになったこと.この8cmの違いは結構大きくて、まさに個人的な趣味性でいったら理想的ともいえるレンズになりました.
なお、雑誌のインタビュー記事にてコシナの方が「画質を追求したレンズなのでフィルタなどはできれば使わないでほしい」との趣旨の発言をしておられたので、I型II型ともに保護フィルタなどはつけていません.I型売却の際にレンズが綺麗だといわれたので、フードもあることですし、まあ問題ないでしょう.
■コンピュータ関連
4月:Keychron Q2Pro

RICOH GR III
キーボードは80%キーボードと呼ばれるKeychronのK8Proをスイッチやキーキャップをカスタマイズして使っていたのですが、ファンクションキーとか使わないキー多いよねと思い、セールのタイミングでよりシンプルな65%キーボードと呼ばれるQ2Proを入手しました.K8Proが黒の筐体だったので今回はホワイトでややソフトなイメージの筐体にしました.
当然ながらここにカスタマイズを加えて、キースイッチはGateronのBabyRaccoon(やや重めのリニアスイッチ)、キーキャップはDropのZambumon MT3というクリーム色にいにしえの端末をイメージした書体にイエローのアクセントの入ったレトロ風に仕上げて使用しています.
6月:iPad Pro M1 12.9inch

RICOH GR III
自宅用iPadとして、2018年に購入したiPad Pro 11inch(第1世代)を使用していましたが、そろそろ買い替えてもいいのでは、そして自宅用なのだからサイズも大きくして12.9インチにしようと思うも、最新型のM4モデルは高価な上に自分の使い方にはあまりにもオーバスペックなので、再整備品として2世代前のM1モデルを購入しました.自宅用といいつつもセルラー対応で通信可能な状況にしてあります.
画質、性能的な面ではまったく不満はありませんが唯一の難点は寝転がって使う時にくるずっしりとした重み.うとうとして顔面に落としたら怪我しそうです.
8月:Logicool MX ERGO S

RICOH GR III
もはや後継は出ないのでは…… とすら思っていた、ロジクールのトラックボールの上位モデル、MX ERGOの新型です.
変更点といえばスイッチがサイレントスイッチになり、充電端子がmicroUSBからUSB Type-Cになったことくらいですが、それでもう十分です.サイレントスイッチは当初はクリック音がなくて違和感がありましたが1,2日ですぐに慣れました.
底面が滑りやすく、固定して使うトラックボールとして動かれては困るので滑り止めを貼り付けて使用しています.
■オーディオ
12月:final S5000

FUJIFILM X100VI
ちょっといいイヤホンがほしいな、とふと思い購入したfinalの新型イヤホンです.購入した真鍮筐体のS5000のほかに、機構的な面は同一でステンレス筐体のS4000があり、店頭で聴き比べてみたところ、思ったよりも違いがあって驚きました.ステンレス筐体のS4000はわかりやすいストレートな音がするのに対して、S5000はちょっと癖のある響きがあり、S4000のほうが万人受けする印象でした.S4000のほうがあらゆる音源を無難に鳴らすのだろうなと思いつつも、個人的に聴き続けてみたいと思ったのはS5000のほうなので、こちらを選びました.
12月:Astell&Kern AK HC3

RICOH GR III
iPadやiPhoneの端子からイヤホン端子がなくなったこともあり、USB Type-C接続のドングル型DACであるAstell&KernのPEE51を使用していましたが、final S5000を購入したので、もうちょっと新しいDACを使ってみようと思い後継機のAK HC3を購入しました.
PEE51と比べてパワフルな音ではあるのですが、どことなく無理に音を鳴らしているような感じもあって聴き疲れする印象がありました.DAC関連のことはあまり詳しくないので調べてみたところ、『ドングル型DAC』と呼ばれるUSB端子に接続してUSB給電で使用するタイプのDACは5V給電で動作しなくてはならないので電源供給面で余裕がないのが難点のようです.
これが次の買い物(物欲)につながります.
12月:iFi audio xDSD Gryphon

Nikon Zf + NIKKOR Z MC 50mm f/2.8
USB給電のドングル型DACではないDACとなると、電源を別途外部から供給するタイプ、またはバッテリ供給タイプのDACということになります.
寝ながら使うことも考慮して電源ケーブルがなくても使いたいと思い、バッテリ供給タイプのDACということで、iFi audioのxDSD Gryphonを選びました.電源供給方法によるものなのかメーカーごとの音作りの違いなのか、AK HC3と比べて角の丸い柔らかな音質だと感じました.
xDSD Gryphonは一般的な有線イヤホンの端子である3.5mmの他にバランス接続と呼ばれる4.4mm端子も搭載しているため、final S5000をリケーブルして4.4mm端子のケーブルに交換したところ、さらに音もよくなりました.
よくなりました…… は結構な話ですが、芋づる式に思わぬ出費が嵩んでしまいました.
■車
4月:MAZDA ND5RE Roadster

Nikon Zf + NIKKKOR Z 24-120mm f/4 S
俗に『ND2』と呼ばれる、ND型ロードスター最大のマイナーチェンジが施されたモデルです.同型の車に乗り換えるのはこれが初めてです.
ND型ロードスターを発売直後に購入していますので9年ほど経過しており、全体的な経年劣化のせいなのか商品改良によるものなのかわかりませんが、試乗した時にはステアリングの滑らかさというか雑味の少なさ、乗り心地によさに驚いた記憶があります.
同じND型にはいずれ買い替えるつもりでいて、車体色が『アーティザンレッドプレミアムメタリック』でタン内装のモデルが出たら買い替えようと思っていたわけですが、ND2型が出て試乗した際に『アーティザンレッドプレミアムメタリック』塗装のMazda6が展示されているのを見かけ、思っていた色とちょっと違うと感じ、ソウルレッドクリスタルメタリックのSレザーパッケージVセレクション(タン内装)を選んだというわけです.その後、35周年記念車が当初思い描いていた仕様そのもので出たわけですが、あっちにしておけばよかった的な思いはさほどないので、この選択でまあよかったかなと思っています.
■家電
2月:BALMUDA ReBaker

FUJIFILM X100V
「まるごとソーセージ」を美味しく温めたい、といういささかとっぴなコンセプトのもとに開発されたトースターです.
惣菜パンやスーパーの揚げ物に特化したトースターということで、自分の生活にはぴったりの製品なので購入しました.
いままでは揚げ物を温めるには電子レンジを使っていましたが、どうしてもパリッとせずイマイチな仕上がりでした.焦げ目もできずにパリパリに仕上がったクロワッサンなどができるのは素晴らしいです.難点は温度調整を微妙に調整しながら温めるのでやや時間がかかることでしょうか.
10月:日立 洗濯機
いままで使っていた洗濯機の挙動が怪しくなってきたというか、モーターの動力をドラムに伝えるパーツのあたりから異音が出るようになってきたので買い替えることにしました.白物家電は使えるだけ使い、機能も必要十分でいいやという方針なので(カメラとかはポンポンと買い替えるくせに)、それほど見当もせず同じメーカー(日立)でいちばんお値打ち価格のものを買ったところ、今まで使っていたものの後継機でした.
11月:Panasonic ジェットウォッシャードルツ

FUJIFILM X100VI
歯磨きには気を使っているつもりなのですが、虫歯があちこちにできてしまい、さらには親知らずも2本抜くことになるなど、もっと歯に対するケアをしなくてはならないと改めて思い知らされました.
かといってフロスはどうも苦手で…… ということで水流によって歯の隙間を掃除する『ジェットウォッシャードルツ』を購入しました.使用当初は口から水がダダ漏れになってしまって水浸しになりがちでしたが、だんだんとうまく扱えるようになりました.舌で触った感じでは隙間もツルツルとした感触なので多少の効果はあるようです.
■その他
1月:GARMIN eTrex Solar

Apple iPhone 13mini
旅行の移動記録をとるのにGPSロガーを長いこと使用しています.いままでGARMINのeTrex 20を使っていましたが、電源が単3電池2本で複数の日数にまたがる旅行などでは電池交換が必要で扱いが面倒だったのでなんとかしたいと思い、充電池式のeTrex Solarを購入しました.
USB Type-C接続による充電に加えてソーラー発電、Bluetooth接続によるログ転送などの機能強化に加えて、受信できる衛星がGPSのみならずマルチGNSS対応ということで他の衛星も受信できて精度や受信までの時間も短縮されました.
eTrex 20に比べて液晶がモノクロになり、地図を保存するデータ領域が減少する(日本地図全図の収録は不可)など機能的に落ちた部分もありますが、基本性能はアップしました.
3月:MONDAINE Evo2 35mm

Nikon Zf + NIKKOR Z MC 50mm f/2.8
欲しいけどまあいいか、を繰り返していたMONDAINEの腕時計.
自分のほしい小径サイズのものがモデルチェンジが行われるようで旧型が安く売られていましたので購入しました.新旧の違いは正直あまりよく分からず、表面的なデザインは変わらないので旧型でまったく問題ないですね.
4月:Organ M-7

これも以前から欲しいと思いつつも様子見していた鞄です.
原材料費の高騰などが理由で価格改定が入るというので購入しました.
革の鞄ということもあり天候の悪い時は持って出れなかったり、サイズ的な問題もあって用途は限定されますがトラ目模様も含めてお気に入りです.
7月:五藤工学研究所 GT-M518

RICOH GR III
『吉田初三郎の世界』展を見に行った際に、単眼鏡で拡大表示している方を数名見かけて、アレいいなと思い購入しました.
五藤工学研究所はプラネタリウムなどを製造している会社で、設立90周年記念ということで製造されたこの製品も光学性能にこだわっているだけあって見やすく、旅行や展示物を見る際などに重宝しています.
8月:GARMIN vivosmart 5

RICOH GR III
歩数や睡眠状況などをトラッキングするデバイスとして、さまざまなものを試してみましたが、最終的に行き着いたのがvivosmart 5です.
最初に買ったFitbit Inspireは運動自動検知はするもののヘルスケア連携せず、次に買ったXiaomi Smart Bandはヘルスケア連携するものの(睡眠データの連携などに一部難あり)運動自動検知はない(検知するものの手動操作で開始させる必要あり)といった問題がありましたが、vivosmartはその両方をクリアしています.
どれが買っていちばんよかったものか、というのは愚問というものでしょう.
2024/12/27

Apple iPhone 13mini
今年の5月、ニコンZマウントのレンズを3本購入した記事において、Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2 Asphericalに対して私はこのように書きました.「弱点…… とまではいいませんがやや残念なのは、最短撮影距離が35cmなこと.食べ物写真を撮るときなどには、あと5cm寄れたらいいのにと思うことがあります.」と.
その後、APO-LANTHAR 35mm F2は販売終了となってしまい、あんないいレンズなのに販売終了とはもったいない…… と思っていたところに、II型の発表がありました.I型との違いは、
・外観を他のVoigtlanderレンズと共通のデザインに揃える
・最短撮影距離を35cmから27cmに縮める
・フードがねじ込み式からバヨネット式に変更(逆さづけ可能)
といったあたりです.最短撮影距離35cmが唯一の弱点と思っていたわけなのですから、することは1つだけです.買い替えです.というわけで予約して発売日当日にI型を下取りに出して受け取ってきました.

Apple iPhone 13mini
デザインについてはとくにI型も悪くないと思っていたのですが、装着してみると結構雰囲気が変わった気がします.

FUJIFILM X100VI
I型の外観.絞り値の数値ごとに塗り分けられていることからも分かるように、FマウントMFレンズのデザインに寄せているのがわかります.

FUJIFILM X100VI
こちらがII型.I型で気になった、マウント部に比べて鏡筒部分が細くてアンバランスな印象がなくなり、結果として鏡筒部分が全体的に太めになりました.ピントリングが大きくなり、逆に絞りリングは狭まりましたが、操作上の違和感はとくに感じられません.全体的にデザインが落ち着いたようにも見受けられます.

FUJIFILM X100VI
買い替えた理由がこれ.最短撮影距離27cmです.光学系はI型II型ともに変更はないとのことで、寄れるようになったのは素晴らしいことです.
ちなみにMFレンズということもあってピント合わせに微調整を要するという目的もあってか、ピントリングの回転は無限遠から最短撮影距離まで270度くらいにもなります.

Nikon Zf + Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2(I型)
絞りF2 1/40秒 ISO640
I型の最短撮影距離35cmで撮影すると、このくらいになります.

Nikon Zf + Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2(II型)
絞りF2 1/40秒 ISO320
II型の最短撮影距離27cmで撮影すると、このくらいまで寄ることができます.
テーブルフォトなどでこのようにして料理を撮影するときにも重宝します.これ以上拡大したいときにはマクロレンズの領域ですね.

Nikon Zf + Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2
絞りF2 1/40秒 ISO140

Nikon Zf + Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2
絞りF2.8 1/40秒 ISO220

Nikon Zf + Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2
絞りF5.6 1/40秒 ISO900
F2解放はもちろん、F2.8とF5.6でも円形となる特殊形状をした絞りリングが採用されています.F4のボケが汚いというわけではないのですが、F5.6メインで撮影し、ぼかしたい時はF2やF2.8を使うことが多くなりました.F2で開放で撮影すると周辺減光があるので、撮影としてうまく使っていきたいところです.

Nikon Zf + Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2
絞りF5.6 1/40秒 ISO220
光学系はそのままなので歪みなどもほぼなく、建築物でも安心して撮影することができます.むしろ、斜めや被写体に正対することなど、撮影する側の腕がシビアに求められます.

Nikon Zf + Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2
絞りF2 1/4000秒 ISO100
Zfのファインダは見やすいのですが、絞り開放ですとピントがシビアなので拡大表示が必須となります.Zfは拡大表示をシャッターボタン半押しで解除できないのがもどかしいところです.早くファームウェアアップデートで対応してほしいところです.

Nikon Zf + Voigtlander APO-LANTHAR 35mm F2
絞りF5.6 1/1600秒 ISO100
Zfの色調設定は、汎用性のあるやや派手目に振ったものと、色調を抑え気味にしたものの2つを使い分けていますが、これは色調抑えめのもの.逆光気味でもあるのでモノクロームにも近い雰囲気があります.使いやすい画角、質感のある描写でお気に入りのレンズです.