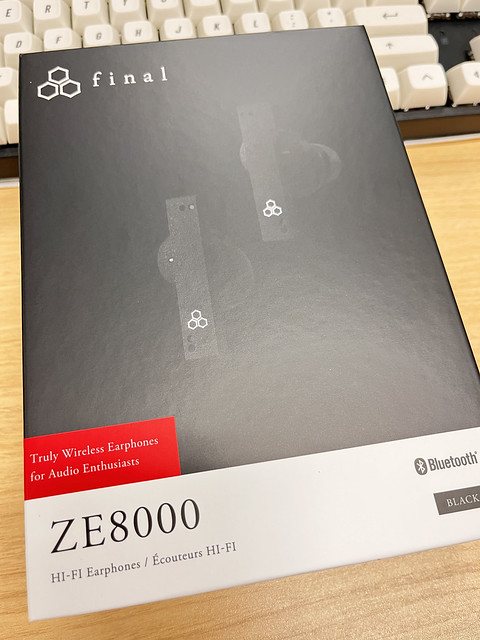2025/12/31
1年を振り返る、物欲篇です.
昨年は大物(ロードスター)を購入したので、それに比べると控えめです.その割に懐具合が寂しいのはやはり物価高のせいでしょうか.
■カメラ・光学
4月:Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical
5月:Nikon MIKRON 6×15 CF
■コンピュータ
9月:Apple iPhone Air
■オーディオ
2月:final ZE8000
3月:final S4000
12月:final TONALITE
■家電
5月:SONY REON POCKET PRO
■その他
5月:MAZDA SPIRIT RACING ドライビングサングラス
9月:SUWADA つめ切り DIAMOND
11月:GARMIN eTrex Touch
12月:Kindle Colorsoftシグニチャーエディション
■カメラ・光学
4月:Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical

CP+で試し撮りして気に入ったレンズです.近い焦点域のレンズとしてVoigtlanderのAPO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical IIを持っていますが、こちらが絞り開放からシャープで隙のない画像であるのに対し、このレンズは絞り解放で柔らかい描写、絞るとシャープな描写となり、変化をつけることができるのが楽しいレンズです.
F値が1.2と明るいレンズなので夜の撮影にも強いのもポイントです.
5月:Nikon MIKRON 6×15 CF

もともとは社内のレイアウト変更によって遠くのホワイトボードを見る必要性があって双眼鏡を買おうと思ったのがきっかけです.
安くていいものも多々ありますが、100年以上前から続くデザインに惹かれてこちらを購入しました.コンパクトでありながら質感が高く重さもあって「いいもの」感がありますね.
基本的には社内に置いてあり、必要に応じて持ち出す感じです.
■コンピュータ
9月:Apple iPhone Air

iPhone 13miniからの買い替えです.小型のiPhoneが欲しかったのですが不人気機種らしく後継機も出る気配がないので、薄型のiPhone Airを購入しました.
世間的には小型のiPhone以上に不人気機種のようですが、個人的には気に入って使っています.
■オーディオ
2月:final ZE8000
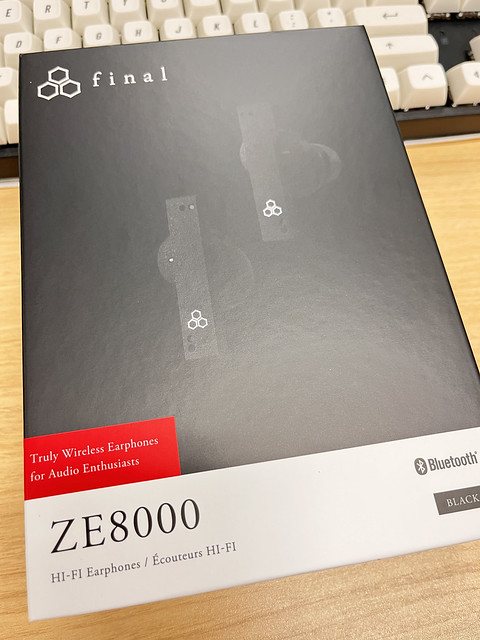
2022年にZE8000を購入し気に入って日々使っていましたが、発売から3年くらい経過したこともあって値段も当初の1/3近くまで下がったタイミングで予備機を購入しました.
後述するように、同じfinalのTONALITEを購入しましたので、こちらはどうしようかという感じです.
3月:final S4000

2024年11月にfinal S5000を購入し気に入って使用しており、同系統のシリーズとしてS4000を購入しました.
フルレンジ2BA機というスペックは同一ながら筐体の素材が異なっており、S5000の真鍮筐体に比べてS4000のステンレス筐体はすっきりとしたクリアな音質なのが特徴です.
12月:final TONALITE

2022年にZE8000を購入してから3年、ワイヤレスイヤホンを変えずに使い続けてきましたが、ここでようやく興味の出たイヤホンが登場したので購入しました.最大の特徴は頭や耳の形状を計測して、その人に合わせた音色に調整してくれる機能を搭載していることです.
調整後に聴いてみると当初は「まあたしかに良くなったかな」というくらいの印象でしたが、調整前の音色に戻すと全然違うという印象を受け、そして様々な曲を聴くと音の違いに驚かされます.
■家電
5月:SONY REON POCKET PRO

自分が使用していた旧型のREON POCKET 3と比べて大幅に機能アップ(と同時にサイズもアップ)したので購入しました.
冷温を伝えるペルチェ素子の面積が大幅に拡大されてバッテリ容量も大型化されたことで、夏場の出勤時などにも旧型では出勤時でバッテリを使い切ってしまっていたのに対して、こちらは帰宅後でもまだバッテリ容量に余裕があり、ギリギリ2日間使えるかなという感じなので使用時間的には4倍程度になっています.
■その他
5月:MAZDA SPIRIT RACING ドライビングサングラス

運転用のサングラスはいくつか購入して試したのですが遮光率が高いとトンネル内で見づらかったりと、なかなかいいものが見つけられなかったのですが、マツダ純正ともいえるこのサングラスは車両開発部門が協力しているとのことでこれなら問題ないだろうと購入しました.
トンネル内でも視界が確保されつつも逆光での使用に耐えられる絶妙さが気に入っています.
9月:SUWADA つめ切り DIAMOND

新潟旅行の際に工場併設の店舗にて購入しました.
爪切りとしての切れ味や機能的な部分は同じですが、サイズやグリップの仕上げなどでバリエーションが用意されています.購入したものはグリップ部分がダイアモンドカットされており、それが気に入って選びました.
11月:GARMIN eTrex Touch

昨年購入したeTrex Solarでログが取れないという不具合が頻発し、どうやら歩行を前提とした製品ということで長距離・長時間の使用には難があるようなので、出たばかりのeTrex Touchを購入しました.
ローエンド機であるeTrex Solarがメモリ容量28MBなのに対して、eTrex Touchは32GBと文字通り桁違いであり、eTrex Solarに比べてカスタマイズ性も高く、動作安定性や記録後のデータ転送面などでも使い勝手が改善されています.
12月:Kindle Colorsoftシグニチャーエディション

いままで使用していたKindle Oasis(2019年モデル)からの買い替えです.
E inkがカラー対応になったのが最大の特徴です.小説を読むのにカラー画面の必要性はないのですが、メールマガジンや漫画なども読むのでやはりカラーは必要だなと感じました.また端子がmicroUSBからUSB Type-Cになったのも大きいですね.
ネックだったのは価格.定価だと44,980円もします.以前は1万円を切る価格だったのを考えると、カラーになったとはいえ高くなったものです.しかしAmazon端末といえば待っていればセールで値下げされるのが常.ブラックフライデーセールで1万円引きになったところを購入しました.
来年の物欲はどうでしょうね.
手持ちのRICOH GR III Diary EditionをGR IVやGR IIIx HDFに変えたいなと思いつつも、7回も抽選に外れている有様ですのでそろそろ当選してもいい頃合いなのではと思うのですが、これだけ人気なので他のメーカーから対抗機が出てもいいような気もするのですが、残念ながらその兆候はなさそうです.
2025/12/21

FUJIFILM X100VI
ワイヤレスイヤホン、final TONALITEを購入しました.
前回購入したワイヤレスイヤホンが2022年12月の同じくfinalのZE8000でしたので3年ぶりとなります.有線イヤホンはあれこれ購入していますが、同じワイヤレスイヤホンを3年も使い続けていたというのはそれだけ気に入っていたということでもあります.
今回購入したのは、finalがワイヤレスイヤホンとして新たなるフラッグシップ製品を位置付けていること、そして後述するカスタマイズ機能に興味を惹かれたからです.
購入にあたってはクラウドファンディングでの早期割引を利用しました.そもそもクラウドファンディングというのは、製品として世に出したいけれど資金調達的に厳しいのを支援するというような位置付けだったような気がしますが、昨今では単なる早割サービス的なものもあるようです.

FUJIFILM X100VI
ケースのサイズは昨今の製品としてはやや大きめ、充電はUSB Type-Cの他にワイヤレス充電にも対応しています.
個体差なのかイヤホンを収納した状態では蓋の締まりがやや甘いですが(蓋を押さえると少しぐらつく)、実用上は問題ありません.

FUJIFILM X100VI
ZE8000は棒状というか直方体のような外見をしていましたが、TONALITEは楕円形のような形をしています.
イヤーピースは「FUSION-G」と呼ばれる製品で遮音性と圧迫感低減を狙った製品です.ややデリケートな作りで雑に扱うと破けやすく、またメーカーとしては3ヶ月ごとの交換を推奨しています.とはいえ、S4000/S5000で1年ほど使っていますが、今のところ交換の必要性は感じていません.

FUJIFILM X100VI
パッケージの中には「DTAS」と書かれた箱が入っています.
これこそがTONALITE最大のセールスポイントであるカスタマイズ機能です.

FUJIFILM X100VI
箱の中にはヘッドバンド、ARマーカーの印刷されたステッカーが入っています.
ヘッドバンドにARマーカー入りのステッカーを貼り付け、頭部や耳の形状を計測することで使用者に合わせて音色を調整することを可能にしています.
finalではZE8000の使用者を対象にした「JDH」(自分ダミーヘッド)というカスタマイズサービスを行なっています.final本社まで出向いて頭の形状を計測してZE8000の音質を最適化してくれるというものなのですが、費用が55,000円と高額であること、川崎にあるfinal本社に2回行く必要があること、そしてなにより抽選制ということもあって敷居が高いサービスなのです.
TONALITEはこれを自宅にいながら行おうという、かなり意欲的というか無謀な製品なのです.

FUJIFILM X100VI
設定にかかる時間は約40分ほど.複数のステップに分かれており、途中で中断も可能です.
大まかには、ARマーカーを貼り付けたヘッドバンドを頭につけた状態の写真をスマホのインカメラで撮影し、TONALITEを耳につけた状態で計測用の音を出してその反響をサンプリングしたデータを送信してfinal側のサーバで解析し、最後に実際に普段聴いている曲を聴きながら違和感のない音色設定を選ぶ、という流れになります.こうして設定を行った情報を「Personalized」としてTONALITEに書き込むことで設定完了です.
カスタマイズを行わない「General」というモードも最初から用意されており、これでも十分高音質だと感じるのですが、「Personalized」した音を聴いたのちに「General」を聴くと違いを感じます.
違いを感じる…… のですが、明らかに「Personalized」の方がよく感じられるものの、その違いを言葉にして表現するのがとても難しいです.「しっくりくる」「馴染む」というような抽象的な表現でしか言い表せないもどかしさを感じます.
高音質なイヤホンをレビューした記事でよく見かける「いままでのイヤホンでは聞こえなかった音が聞こえる」というのは確かにあって、ボーカルが歌い出す前の息を吸い込む音や細かなニュアンスを感じ取ることはできると思いました.また、音の濁りのようなものがかなり軽減されているのも「いい音」の要因に感じました.
ZE8000に比較してノイズキャンセリング性能も向上しており、ワイヤレスイヤホンという「言い訳」を必要としないほどの高音質で、不満のまったくない製品です.当面はこれが外出時の必需品となりそうです.
2025/12/13

FUJIFILM X100VI
AmazonのブラックフライデーセールのタイミングでKindle Colorsoftを購入しました.
カラー版のKindleということで発売当初から欲しいなと思ってはいたのですが、読書端末として考えると高価で、なおかつそれまで使用していたKindle Oasisのようにページ送り/戻しのハードウェアボタンがないことが気になって購入に至らず様子見をしていました.
しかしながらブラックフライデーのセールで通常価格44,980円が34,980円と1万円引きになったこと、ハードウェアボタンを備えたOasisの後継が出る様子もなさそうということで購入することにしました.

FUJIFILM X100VI
いっしょに純正のファブリックカバーと保護フィルムを購入.周辺機器類はセールの対象外なので、結果的には合計で4万円を超える額になってしまいました.

FUJIFILM X100VI
パッケージを開けた状態.カラー画像が表示されています.
Kindleのディスプレイに採用されているE-inkは書き換え時のみ電力を消費するので、画面表示したまま届けられるわけなのです.
使ってみた感想です.
画面がカラーになった以外は従来のKindleと変わらないですね.レスポンスも多少速くなったとはいえ、何枚かおきに反転して書き換えが発生しますし.
また商品名に「Colorsoft」とあるように、液晶や有機ELのような鮮やかなカラーではなく、例えるならばわら半紙にインク節約モードで印刷したかのような地味な風合いです.とはいえ、カラーになった恩恵は大きく、カラーの資料画像付きの本などを読むときに、モノクロでは判別不可能だったところもしっかりと認識できます.
モノクロ部分が従来通り300dpiで表示されるのに対してカラーは150dpi表示になること、ディスプレイにカラーフィルタが挟まることで文字のくっきりとした描写がモノクロモデルより劣るという評価もあるようですが、自分の目では気になりませんでした.
Kindle Oasisから変わった点として見逃せないのが、端子がmicroUSBからUSB Type-Cになったことです.充電頻度は少ないとはいえ、他の端末とケーブルが使い回しできるのはやはり便利です.
2025/11/23

RICOH GR III
GPSロガーとしてGarminのeTrex Touchを購入しました.
2024年頭にGarminのeTrex Solarを購入してGPSロガーとして使用してきたのですが、いくつか重大な問題がありました.
・記録しているはずのログが部分的に記録されていないことがある
・記録容量が少ない(28MB)
・使用時に地図が表示されない(上記記録容量が少ないため地図データを格納できない)
・総移動距離表示が一定距離(168km)を超えると更新されなくなる(のちにファームウェアアップデートで解消)
・ソーラーパネル内蔵で充電しながら使えるものの、日差しが強すぎると熱でハングアップする
とくに記録しているはずのデータが部分的に記録されないのは致命的で、偶然かと思いますが自分の旅行記録でも再訪できるか微妙な場所(例:津軽岩木スカイライン、弥彦山スカイライン、白馬から糸魚川に抜ける国道148号など)が記録されておらずがっかり、ということがありました.厄介なことに記録中に画面で確認することができないため、帰宅して取り込んでからデータ欠落していることに気づくわけです.
メモリが28MBしかないことや、途中でファームウェア更新で修正されたとはいえ、総移動距離が168km以上は表示されないことを見るに、長距離のログを取ることやトレッキングナビを目的とした製品ではないらしく、歩行用レベルの機能しか有していない製品といえるもので、以前に使用していたeTrex20と比べても機能的に劣っていると言わざるを得ません.
これでは困る、ということで代替品を探していたところ同じGarminから上位モデルといえるeTrex Touchが発表になっていたので購入しました.

RICOH GR III
eTrex Solarとの違いとしては、
・タッチパネル式カラー液晶を搭載
・記録容量32GB
・日本地図データを収録
・画面等の詳細なカスタマイズが可能
ということで、記録容量が1,000倍あまりになっていることからもわかるように、別物といえる製品に仕上がっています.
また、アクティビティの種類として「ドライブ」が選択できることからも、長距離移動も考慮した設計になっていると思われます.

Apple iPhone Air
実際に2台を持ち出して日帰り旅行で試してみました.
衛星の補足については大きな違いはなく、トンネルを出たときなどで場合によってはeTrex Solarのほうが先に位置情報を取得することもありました.
またeTrex Touchは移動していない場合には記録をオフにする機能があり(移動を検知する速度は変更可能で初期値は1.6km/h)、そのため鉄道での移動時にも駅停車時に記録が一時的に中断するので、停止時に位置情報のずれでログがぐちゃっとするのを防ぐことができます.
200kmを超える移動も含めて数回試してみましたが、いまのところデータの消失などもなく、安定したログが取れている印象です.気になった点としては、タッチパネルの反応がよすぎるため、鞄から下げているような状態でも意図せず画面表示が切り替わってしまうことがありました.誤って記録停止などが起きないようにするため、タッチパネル操作ロック(唯一の物理ボタンである電源スイッチを押すまで解除されない)が必須といえそうです.それ以外は満足のいく製品といえます.
2025/10/19
半年ほど前ですが、Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Asphericalを購入しました.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/80秒 ISO100
きっかけは今年3月に行った、CP+のコシナブースでこのレンズを試したことでした.
当時、メインのレンズとして同じVoigtlanderのAPO-LANTHAR 35mm F2を使用していました.解放からキレのいいレンズでII型になって最短撮影距離が27cmまで寄れるようになるなど、焦点距離含め自分にとっては理想のレンズです.
が、このNOKTON 40mm F1.2は絞り開放時の「ユルさ」「柔らかさ」がAPO-LANTHARにはない魅力でした.それでいて絞ればキレのよさもあり、絞り値によって描写を変えられるのが気に入り、購入することにしました.
少し気になったのは焦点距離.個人的に好みの焦点距離は28mmから35mmくらいなので40mmだと望遠寄りかなと思いましたが、CP+で触った時もそれほど違和感がなかったので購入に踏み切りました.

Apple iPhone 13mini
F1.2という明るいレンズながら前玉はそれほど大きくないですね.フィルタ径は58mmでAPO-LANTHAR 35mm F2と同じです.Voigtlanderのレンズキャップはバネが弱いのと引っ掛かりがよくなくて外れやすいので予備を常備しているのですが、使い回しできるので助かります.
モダンクラシックなデザインのレンズで、Zfとの組み合わせで違和感がありません.絞りリングは先端寄りにあり、細めですが操作しやすいです.

Apple iPhone Air
フードはねじ込み式で、内側にネジが切ってあって58mmフィルタが取り付けできるようになっています.なのでフィルタをつけても全長が伸びません.ただし、つけ外しはしづらいので一時的に使うようなフィルタはレンズとフードの間につけたほうがよさそうです.
自分は日中の屋外でも絞りF1.2解放で使えるようにND8フィルタをつけています.室内や屋外でも暗くなって光量の低い環境ではフードごと外して撮影しています.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/200秒 ISO100
絞り解放、最短撮影距離で撮影.収差で霧がかかったかのようにふわっとボケています.しかしながらピントの合っている部分はしっかりと描写されています.昔の単焦点大口径レンズは絞り解放で撮影距離が短いとピントの合っているところも収差がありすぎてユルく、2段くらい絞らないと使えなかったりしたものですが、これであれば解放から使っていけます.ただし、ピントの合っている範囲が狭すぎるので必要に応じて絞った方がいいでしょうね.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F5.6 1/800秒 ISO100
屋外でF5.6まで絞って撮影.同じレンズとは思えないほどキレのいい描写です.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/1600秒 ISO100

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F2 1/800秒 ISO100
絞り解放ですと周辺減光が強めに出ます.F2まで絞るとほぼ気にならなくなります.
周辺減光も描写表現として変化がつけられて気に入っているところです.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/1250秒 ISO100
絞り解放で撮影.こうした花の撮影などでは収差がプラスに働きますね.
ピントの合っているところもふわっとしていますが、ピントの芯はしっかり出ているのがいいですね.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/1600秒 ISO100
同じく絞り開放ながら、やや離れたところにピントを合わせると収差も抑えられた描写になります.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F7.1 1/40秒 ISO1400
画角40mmなのと、最短撮影距離30cmなので新幹線などでテーブルのものを撮影するのにちょっと引きが足りないかなと感じる部分はあります.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F2 1/40秒 ISO360
F2まで絞って撮影.1段半絞ることで周辺減光も控えめになり、近接域でも安定した画質になります.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/125秒 ISO250
ふわっとした収差、ピントの合っている場所の存在感、周辺減光が相まって立体的な描写を感じます.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/2000秒 ISO250
ややノスタルジックな色味で撮影したら、ジオラマを撮影したかのような雰囲気が出ました.

Nikon Zf + Voigtlander NOKTON 40mm F1.2 Aspherical Z-Mount
F1.2 1/40秒 ISO2000
夜を意味するNoktから名付けられたNOKTONだけあって、夜の撮影でも絞り解放F1.2が威力を発揮します.
夜間の神社の薄暗い照明でも絞り解放、1/焦点距離のシャッター速度でもISO2000で撮影できるのは明るいレンズならではです.
同じVoigtlanderでもAPO-LANTHAR 35mm F2は絞り解放からシャープな画質で、絞りはシンプルにボケ具合を加減するものという性質なのに対し、このNOKTON 40mm F1.2は画質のユルさやシャープさ、周辺減光による空気感のようなものまで絞りで調節できる自由度を感じます.